このページに記載された情報通り観察できるかどうかは状況次第です。
特に鳥類は飛翔能力があるため、撮影後すぐに移動することが考えられます。ご了承願います。
お待たせしました!
2026年02月17日
●ニホンアカガエル産卵!
●ズグロカモメ夏羽
●カワウ繁殖羽 ●キジ ●ただカモメ
※YouTube Facebook Instagramにご登録願います!
それぞれ左端のバナーから閲覧できます。

ニホンアカガエル卵塊

ニホンアカガエル卵塊

ニホンアカガエル
お待たせしました! きらら浜にやっと春がやって来ました!
本日、今シーズン初となる「ニホンアカガエルの卵塊」をビオトープで確認しました!
日曜日に成体の確認はできていたので、もうすぐと思っていて
昨日も見に行ったのですが、その時点では確認できませんでした。
そして、今日やっと嬉しいニュースをお届けすることとなりました。
実は過去10年の中で今年が最も遅い確認なので、嬉しさは例年以上のものとなりました。
ただし、ちょっと気になるのが2枚目の卵塊の画像で
1枚目と比べて泥が被っているのと、白くなって死んでいるようなものがあることです。
新鮮味に欠けるので、もしかすると見落としていたのかもしれません...
それと、今日は3つ卵塊を見つけたのですが
盛り上がりに欠けベチャっとしていたのも気になります。
とはいえ、なんとか今年の卵塊初確認となりました。
今後、その数は次第に増えていくことでしょう。

ズグロカモメ

ズグロカモメ
お待たせしました!春がやってきました!!!の第2弾もあります!
「ズグロカモメの夏羽個体」が干潟で観察できました。
「ズグロ=頭黒」という名前がついていますが、これは夏羽の状態に当てはまるもので
越冬のため10月に姿を現してからこれまでは、頭は冬羽の白い状態でした。
そして、今日はかなり黒い夏羽へと進んだ個体を確認できたのです。
それもそのはず。既に立春から10日以上経っているので
生き物たちは日照時間が長くなったことから春を感じ取っているのでしょう。
1枚目の手前は羽色から成鳥で、奥は幼鳥です。
頭羽が黒くなるのは成鳥の方が早いとされているので
教科書通りの進み具合というのも面白いものです。
ズグロカモメは韓国や中国の沿岸部を中心に繁殖するため
4月くらいまでには渡ってしまいます。
夏羽と冬羽を比べながら観察してみてください。

カワウ

キジ
春がやってきました!
第3弾は「繁殖羽のカワウ」と「そわそわし始めたキジ」です。
山口県のカワウはこれから夏にかけて繁殖期となりますが
オスもメスもお互いへのアピールのため、白髪のような白い羽毛に変身します。
公園内でも、その様な「着飾ったカワウ」をちらほら見かけるようになりました。
頭部の羽毛だけでなく、足下にも白い羽毛が出てくるので注意して見てください。
もうひとつは「そわそわし始めたキジ」の話題。
彼らも繁殖モードへと少しずつ変わってきています。
キジの場合はオスが縄張り宣言とメスへの求愛のため
♪ケーン ケーン♪と鳴くだけでなく
「母衣(ほろ)打ち」という羽を胸に打ち付けてバタバタと音を出す行動をとります。
いつもは警戒心が強く、人の目に触れないように生活していますが
繁殖期となると、ここぞとばかりに目立つ所で縄張り&求愛宣言をするようになるのです。
そのため、遭遇する確率もグッと上がるので、皆さんも探してみてください。
今回は中央園路の水路沿い、ヨシ焼きのために草を刈った火道で出会いました。

カモメ

カモメ
最後は、きらら浜ではレアな「カモメ」です。
・クチバシは淡い黄色で、ほぼ模様は無い。いかつい感じもありません。
・セグロカモメ?と思いきや、だいぶ小さく、足は黄色。
・後頭部の辺りに淡褐色の斑が少しあります。
・風切り羽の模様は白黒灰色で構成された3パターンほど。
総合すると、いわゆる「カモメ」ということが分かります。
公園で冬の間毎日の様に見かけるカモメは「ズグロカモメ」で
その次に、たまに見かけるのが「ユリカモメ」と「セグロカモメ」となり
今回観察できた「カモメ」は、まぁレア種となります。
カモメの仲間は似た様な模様のものが多いので慣れないと識別に迷いますが
きらら浜周辺であれば、この「カモメ」と「オオセグロカモメ」も含めて考えると
だいたいは識別できると思います。
ちなみに、今回の観察場所は土路石川でした。
さぁ、春らしくなってきたきらら浜へ、ぜひ、遊びにいらしてください。(Shigeru-tan)
「晴れ・時々・雪」
2026年02月08日
●晴れ間に映えるエナガちゃん。
●雪降る中のミサゴとカワウ
※YouTube Facebook Instagramにご登録願います!それぞれ左端のバナーから閲覧できます。

ビオトープ雪景色

エナガ
全国的に記録的な降雪予報が出る中
公園のある阿知須でも未明から断続的に雪が降っていて
ビオトープのデッキ等は、少しだけ雪景色が見られました。
開園前の晴れ間にはエナガを撮影することもできました。

カワウ

ミサゴ
晴れ間があるからといって油断をしていると
西の空にあった雪雲が、あっと言う間に公園に掛かり
どんよりした鉛色の景色の中、雪が降り始めます。

カワウ

ミサゴ
一番激しく降ったのは午前9時頃で、上2枚の画像がその時のものです。
この後も夕方まで降雪予報が出ているので、お出かけになる際はご注意ください。
さて、今日は目まぐるしく天気が変わるだけでなく
気温が日中でも5℃に届かず極寒の1日となりましたが
火曜日位からは最高気温が10度を超える予報が出ているので
次第に春らしくなっていくものと思われます。
ぜひ、遊びにいらしてください。(Shigeru-tan)
最近のクロツラヘラサギとヘラサギ
2026年02月03日
※YouTube Facebook Instagramにご登録願います!それぞれ左端のバナーから閲覧できます。
度々お伝えしている「クロツラヘラサギ」と「ヘラサギ」ですが
1月は毎日10羽位の群れとなって公園の干潟に姿を現しています。
そこで、撮り溜めていたものも含めて状況を掲載します。

クロツラとヘラサギ
ヘラサギとクロツラ
クロツラヘラサギ
「クロツラヘラサギ」と「ヘラサギ」が互いを羽繕いする「ほっこり」する様子は
元旦の観察速報でも話題にしましたが再度別角度で撮影したものを載せてみます。
頭や喉は自分の足を使ってかゆい所をかくことはできても羽繕いとなると難しく
仲間の手助けが必要で、私たちから見ても「ほっこり」していいものですね。
また、元旦に撮影した
「クロツラヘラサギとヘラサギが互いを羽繕いするほっこり動画」をYoutubeに投稿したので
お時間のあるときにでもご覧になってください。
「クロツラヘラサギとヘラサギがお互いを羽繕いするほっこり動画」in 新光産業きらら浜自然観察公園

クロツラヘラサギ
クロツラとヘラサギ
この2種の虹彩(目)は成鳥になるにつれ「より赤く」「より澄む」ため
年齢と光の加減によって、とても印象的な鮮やかな赤を感じることができます。

ヘラサギとクロツラ
ヘラサギとダイサギ
6枚目(左)の画像は3羽が並んでいる様子が
なんだか、人間が手を差し出して「がんばるそーっっ!」と言っているときの様で
これまた「ほっこり」感じたものです。
7枚目(右)はヘラサギとダイサギのツーショットです。

クロツラとヘラサギ
クロツラとヘラサギ
「クロツラヘラサギ」と「ヘラサギ」の群れは干潟の奥にある
クロツラヘラサギ・リハビリセンターの周辺で満潮時に休んでいることが多いので
ご来園された場合はそちらの方を探してみてください。
本日2/3(火)は「節分」、明日2/4(水)は「立春」。
これから日の出の時間も次第に早くなり、春を感じることでしょう。(Shigeru-tan)
1月は毎日10羽位の群れとなって公園の干潟に姿を現しています。
そこで、撮り溜めていたものも含めて状況を掲載します。

クロツラとヘラサギ

ヘラサギとクロツラ

クロツラヘラサギ
「クロツラヘラサギ」と「ヘラサギ」が互いを羽繕いする「ほっこり」する様子は
元旦の観察速報でも話題にしましたが再度別角度で撮影したものを載せてみます。
頭や喉は自分の足を使ってかゆい所をかくことはできても羽繕いとなると難しく
仲間の手助けが必要で、私たちから見ても「ほっこり」していいものですね。
また、元旦に撮影した
「クロツラヘラサギとヘラサギが互いを羽繕いするほっこり動画」をYoutubeに投稿したので
お時間のあるときにでもご覧になってください。
「クロツラヘラサギとヘラサギがお互いを羽繕いするほっこり動画」in 新光産業きらら浜自然観察公園

クロツラヘラサギ

クロツラとヘラサギ
この2種の虹彩(目)は成鳥になるにつれ「より赤く」「より澄む」ため
年齢と光の加減によって、とても印象的な鮮やかな赤を感じることができます。

ヘラサギとクロツラ

ヘラサギとダイサギ
6枚目(左)の画像は3羽が並んでいる様子が
なんだか、人間が手を差し出して「がんばるそーっっ!」と言っているときの様で
これまた「ほっこり」感じたものです。
7枚目(右)はヘラサギとダイサギのツーショットです。

クロツラとヘラサギ

クロツラとヘラサギ
「クロツラヘラサギ」と「ヘラサギ」の群れは干潟の奥にある
クロツラヘラサギ・リハビリセンターの周辺で満潮時に休んでいることが多いので
ご来園された場合はそちらの方を探してみてください。
本日2/3(火)は「節分」、明日2/4(水)は「立春」。
これから日の出の時間も次第に早くなり、春を感じることでしょう。(Shigeru-tan)
「ホシゴイ」登場!
2026年01月24日
※YouTube Facebook Instagramにご登録願います!それぞれ左端のバナーから閲覧できます。

ゴイサギ
淡水池の水際で「ゴイサギ」の幼鳥を見つけました。
羽毛は灰褐色で周囲の色と似ていて分かりづらいのですが
淡いながらも黄色の足が目立ったので気づくことができました。
「ゴイサギ」は濃紺・白・グレーの羽毛で、目(虹彩)は赤い、とてもきれいな野鳥ですが
巣立った時の幼羽は、この画像の様な色合いなのです。
点々とある白っぽい斑が、まるで夜空の星のように見えるため
別名「ホシゴイ」とも呼ばれています。
似た様な色のアオサギの首はとても長いですが
ゴイサギはそれ程長くはなく
休憩中に首を縮めているときは、ズングリとした愛嬌あふれる姿で人を魅了します。
暗い時間帯に活動することがほとんどなので
日中、公園内で見つけることは多くありません。(Shigeru-tan)
※さて「ホシ(星☆彡)ゴイ」の紹介をしたので
1/31(土)に予定している「冬の天体観察教室」のお知らせです。
気になる方は以下から募集チラシをご覧ください。
冬の天体観察教室 募集チラシ.pdf
宜しくお願いいたします。
昨日ツクシガモがやってきました!
2026年01月23日
その他
●シメ ノスリ ヨシガモ
●氷の花が咲きました!
※YouTube Facebook Instagramにご登録願います!それぞれ左端のバナーから閲覧できます。

ツクシガモ
昨日の情報です。
淡水池に2羽の「ツクシガモ」が来ていたとTryレンジャーから報告があり
画像を託されました。
公園周辺では、まぁ、観察されているカモの仲間ですが
園内に入ってくることは、ほとんどないので、観察できるとラッキーな野鳥です。
ご覧の通り白い部分が多いので
遠目に見ると「なんだ、あの白い鳥は?」と目立つので、すぐに気づくことでしょう。

ヨシガモ
珍しくはないけれど、園内で見かけたら、ちょっと嬉しいカモの話題をもうひとつ。
今朝、ヨシ原池で見かけた「ヨシガモ」です。
今年は園内を利用するマガモの数が例年に比べやや多く
オスは緑色の頭をしていますが
「ヨシガモ」は同じ緑色の頭でも、少し茶色っぽく見えたり
クチバシの色は黒で、オスのマガモの黄色とは違います。
また、尾羽の様に長く見える三列風切羽も特徴的。
さらに、後頭部の羽も長いので、フォルムも違って見えます。
今朝は50羽程のマガモの中に、たった1羽でしたが確認できました。

シメ

ノスリ
その他、「シメ」も園内では、いつも観察できる野鳥ではありません。
それでも今年は度々観察でき、今朝もツグミの群れと一緒に行動していました。
太くてしっかりしたクチバシで、固い木の実を割ることもできるのです。
それと、珍しく「ノスリ」が干潟に降りていました。
何か小鳥でも捕まえたのかと思って撮影しましたが
何も映っていなかったので、もしかすると捕獲に失敗して「呆然」としていたのかも。
その他、今朝は「ハイイロチュウヒ」のオスとメスも観察できました。

氷のアート

氷のアート

氷のアート
日本列島が大寒波と大雪で警戒する中
ビオトープでは「氷の花」が咲いていました。
シモバシラというシソ科の植物でも
寒さのため茎の中の水分が膨張して、外に染み出るときに凍って起こる
「シモバシラ」という現象があり
今回のものと似ていますが同じ仕組みなのかはよく分かりませんでしたが
「氷のアート」に感動したひとときでした。
さて、まだ数日は続くこの大寒波で
いつもと違った野鳥たちが姿を見せてくれるのか
注意して観察していきたいと思います。(Shigeru-tan)
(全2126件のうち、1件目から5件目を表示中) 1
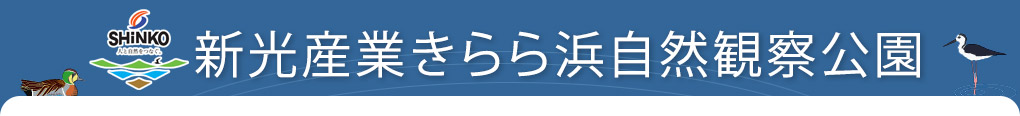





 新光産業きらら浜自然観察公園
新光産業きらら浜自然観察公園